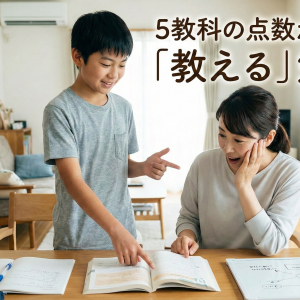不登校児童生徒は年々増加しており、大きな社会問題となっています。文部科学省の発表では2012年に約11万人だった不登校児童生徒は2023年には約35万人となっています。不登校の前段階にあたる「行き渋り」や「五月雨登校」という言葉があります。今回は不登校の状態を表す言葉について説明します。
不登校のお子さまの状態を正しく知ろう不登校の類義語ってどんな種類があるの

1.はじめに
2.不登校を表す言葉
・五月雨(さみだれ)登校・行き渋り
この2つは完全に不登校ではなく学校に行く日と行かない日がある状態をさす言葉です。不登校と言われるのは年間30日以上欠席してからです。この2つをあわせると不登校の児童生徒はより多くなります。
・積極的不登校
以前は不登校=学校に「行けなくなった」という認識を持ってる方が多いものでした。しかし、オンライン授業の普及による学びの場の増加や考え方の多様化により現在は学校に「行かない」という選択を取られる方が増えました。通信学習やフリースクールを活用して、出席扱い制度を利用する方もいます。
・登校拒否
上記の積極的不登校と同様の意味合いで使われることが多いです。以前は不登校ではなく登校拒否という言葉が一般的でした。しかし拒否という言葉がマイナスイメージを想起させるということから不登校という言葉が一般的となりました。以前は拒否せざるをえなかったという意味合いで、現在は自らの意思で拒否したという意味合いとして使われています。
3.まとめ
お子さまが不登校になったとき、保護者はとても不安になります。不登校のお子さまに関わる方はお子さまの状態に合わせた正しい言葉を選択して保護者の方が安心できるサポートをするように心がけましょう。
無料体験に申し込みたい方
・五月雨(さみだれ)登校・行き渋り
この2つは完全に不登校ではなく学校に行く日と行かない日がある状態をさす言葉です。不登校と言われるのは年間30日以上欠席してからです。この2つをあわせると不登校の児童生徒はより多くなります。
・積極的不登校
以前は不登校=学校に「行けなくなった」という認識を持ってる方が多いものでした。しかし、オンライン授業の普及による学びの場の増加や考え方の多様化により現在は学校に「行かない」という選択を取られる方が増えました。通信学習やフリースクールを活用して、出席扱い制度を利用する方もいます。
・登校拒否
上記の積極的不登校と同様の意味合いで使われることが多いです。以前は不登校ではなく登校拒否という言葉が一般的でした。しかし拒否という言葉がマイナスイメージを想起させるということから不登校という言葉が一般的となりました。以前は拒否せざるをえなかったという意味合いで、現在は自らの意思で拒否したという意味合いとして使われています。
お子さまが不登校になったとき、保護者はとても不安になります。不登校のお子さまに関わる方はお子さまの状態に合わせた正しい言葉を選択して保護者の方が安心できるサポートをするように心がけましょう。
無料体験に申し込みたい方