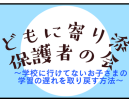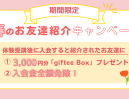不登校児童生徒は年々増加しており、大きな社会問題となっています。文部科学省の発表では2012年に約11万人だった不登校児童生徒は2022年には約30万人と増加しました。
不登校になった際に保護者の悩みとして多いのが家庭学習に取り組ませるのかについてです。今回は不登校児童生徒が勉強に対してどのような気持ちを抱いているのかとどのように家庭学習に取り組ませたらいいのかを説明いたします。
2025年度に向けて2024年度からできる準備不登校のお子さまや家庭学習との向き合い方

1:増加する不登校児童生徒
2:成功体験と環境
文部科学省の調査では学習をきっかけとした不登校は4.9%とそれほど多くありません。しかし、文部科学省の別の調査では不登校生徒で勉強の遅れに対する不安があったと答えた生徒は74.2%、進学進路に対する不安があったと答えた生徒は69.2%です。このことから勉強が不登校の直接のきっかけとなる割合は少ないものの、勉強への不安から学校に戻りにくいと感じる人の割合が増加することが予測されます。不登校児童生徒が復学しやすくなるために家庭学習で不安の一部を解消しておくことは良いことです。
勉強に取り組ませたいときに大事なことは2つあります。
(1)目的意識を持たせること
勉強しなさいと押し付けてはいけません。お子さまは勉強をしないといけないことはわかっていても理由まではわかりません。自信をつけるため、学校に戻るため、進路の幅を広げるためなどお子さまにあった目標をお子さまと設定し
てください。
(2)自信をつけさせること
特に復学をしてほしい保護者の方は早く学校に追いつくように現学年と同じところから始めたいと思う方が多いです。お子さまが現学年の内容を理解できているのであれば大丈夫ですが難しい場合は焦らず前の学年から取り組みましょう。お子さまが不登校になっているときは勉強に対する自信をなくしている可能性が高いです。お子さまが前向きに取り組めるようにまずはできるところから取り組みましょう。
3:まとめ
お子さまが不登校になったときに家庭学習を無理して取り組む必要はありません。しかし、学習に取り組むことでお子さまに新しい考えが生まれるかもしれません。まずは学習の一歩目のきっかけを与えてあげてください。
無料体験に申し込みたい方
文部科学省の調査では学習をきっかけとした不登校は4.9%とそれほど多くありません。しかし、文部科学省の別の調査では不登校生徒で勉強の遅れに対する不安があったと答えた生徒は74.2%、進学進路に対する不安があったと答えた生徒は69.2%です。このことから勉強が不登校の直接のきっかけとなる割合は少ないものの、勉強への不安から学校に戻りにくいと感じる人の割合が増加することが予測されます。不登校児童生徒が復学しやすくなるために家庭学習で不安の一部を解消しておくことは良いことです。
勉強に取り組ませたいときに大事なことは2つあります。
(1)目的意識を持たせること
勉強しなさいと押し付けてはいけません。お子さまは勉強をしないといけないことはわかっていても理由まではわかりません。自信をつけるため、学校に戻るため、進路の幅を広げるためなどお子さまにあった目標をお子さまと設定し
てください。
(2)自信をつけさせること
特に復学をしてほしい保護者の方は早く学校に追いつくように現学年と同じところから始めたいと思う方が多いです。お子さまが現学年の内容を理解できているのであれば大丈夫ですが難しい場合は焦らず前の学年から取り組みましょう。お子さまが不登校になっているときは勉強に対する自信をなくしている可能性が高いです。お子さまが前向きに取り組めるようにまずはできるところから取り組みましょう。
お子さまが不登校になったときに家庭学習を無理して取り組む必要はありません。しかし、学習に取り組むことでお子さまに新しい考えが生まれるかもしれません。まずは学習の一歩目のきっかけを与えてあげてください。
無料体験に申し込みたい方